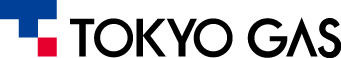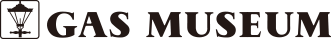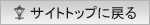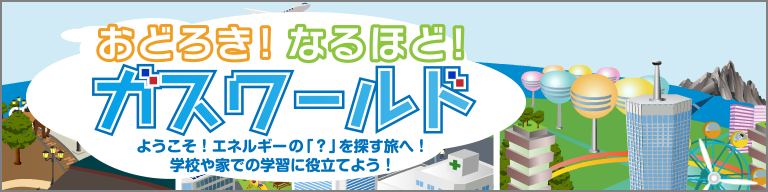渋沢栄一とガス事業 -「公益追求」実践の軌跡-
Episode エピソード4「暮らしを豊かに」
一般家庭向けに新たな生活価値を創出した国産ガス機器の投入
明治20年(1887)に東京で電灯事業が開始され、ガス灯の新たな競争相手となりました。しかし、当時の電灯は電球の寿命の短さや停電のリスクから、ガス灯が依然優位であり、明治30年代から大正初期にかけてガス灯は全盛時代を迎えます。

渋沢栄一 70歳の肖像
龍門雑誌第270号附録
「青淵先生七十壽祝賀記念号」より
明治43年(1910)
一方で渋沢栄一は、明治29年(1896)に、技師長である中川五郎吉をガス事情調査のため欧米へ派遣し、「今後のガス需要は『熱源利用』が主流となる」との認識を得ます。
この結果をふまえ、「一般家庭の炊事用途向けにガスを普及させる」方針を決定し、ガス灯が優位であった明治30年(1897)から既に、ガス熱源利用の新分野開拓へと踏み出していました。
家庭用の炊事需要創造の端緒となったのが、日本の食生活に欠かせない炊飯分野でした。東京瓦斯は自社で日本初の国産品開発に取り組み、明治35年(1902)に国産ガス機器の特許第1号「瓦斯かまど」を発売します。
さらに、暖房分野(瓦斯火鉢)、風呂分野(瓦斯風呂)でも国産ガス機器の開発を進めていきます。

明治時代のグルメ本「食道楽」に登場する大隈重信邸のガス化された台所。図中右側に、大小三つのガスかまどが描かれている
大隈重信伯爵邸の台所 村井弦斎「増補注釈 食道楽 春の巻」より 明治36年(1903)

北里柴三郎邸の浴室。角型ガス風呂と室内を温めるガスストーブ置かれている
東京瓦斯二十五年記念写真帖より 明治43年(1910)

「4升炊きガスかまど」 明治後期

「瓦斯火鉢」
カタログ「瓦斯熱用具」より
明治41年(1908)

「角型瓦斯風呂」
カタログ「瓦斯器具案内」より
明治43年(1910)

明治40年(1907)に開催された東京勧業博覧会の「瓦斯館」

館内部では国産品のガス器具を展示してPRに努めた
「瓦斯館陳列室(其一)會社製品」
東京瓦斯株式会社 沿革及事業成績より 明治40年(1907)